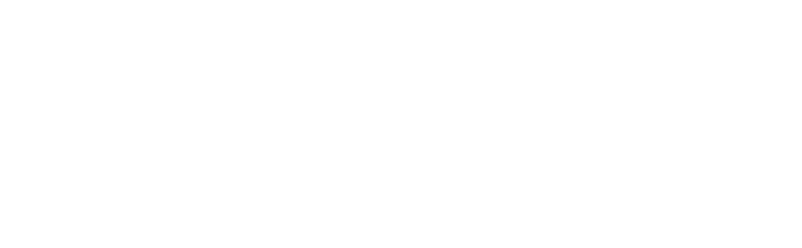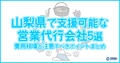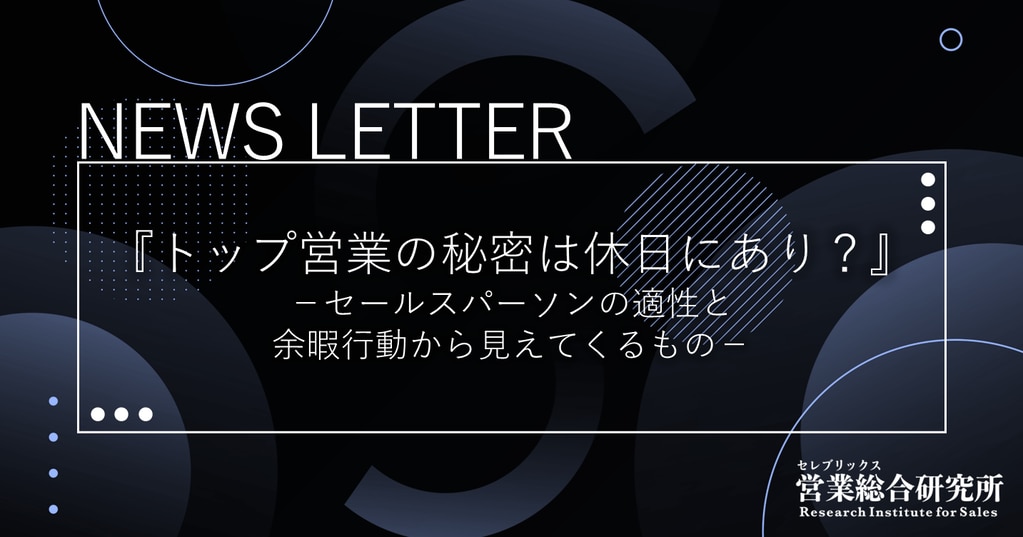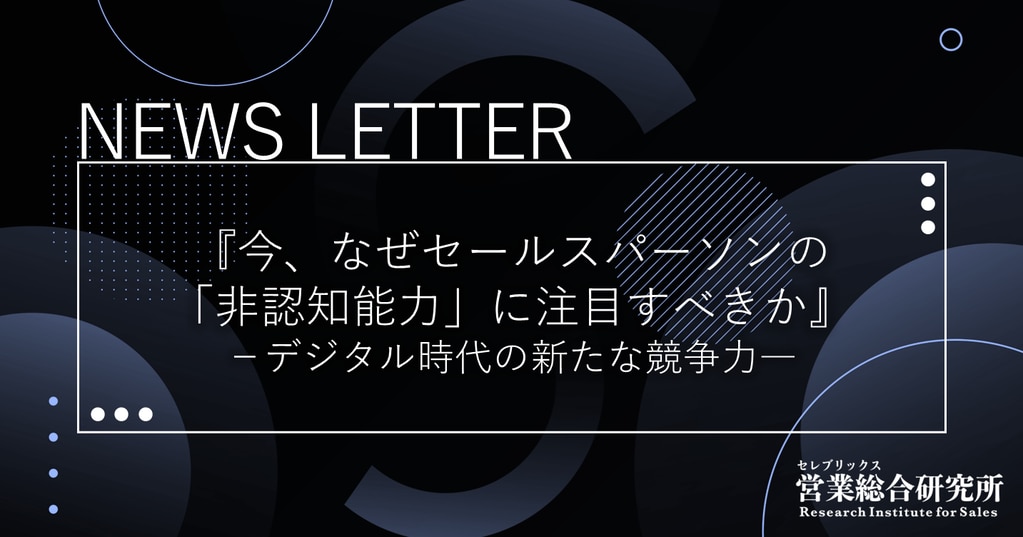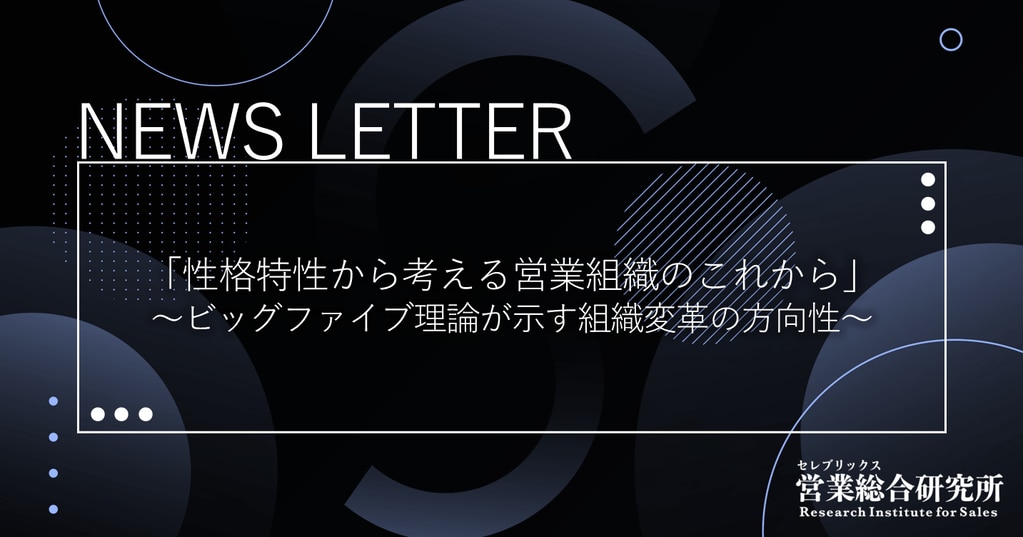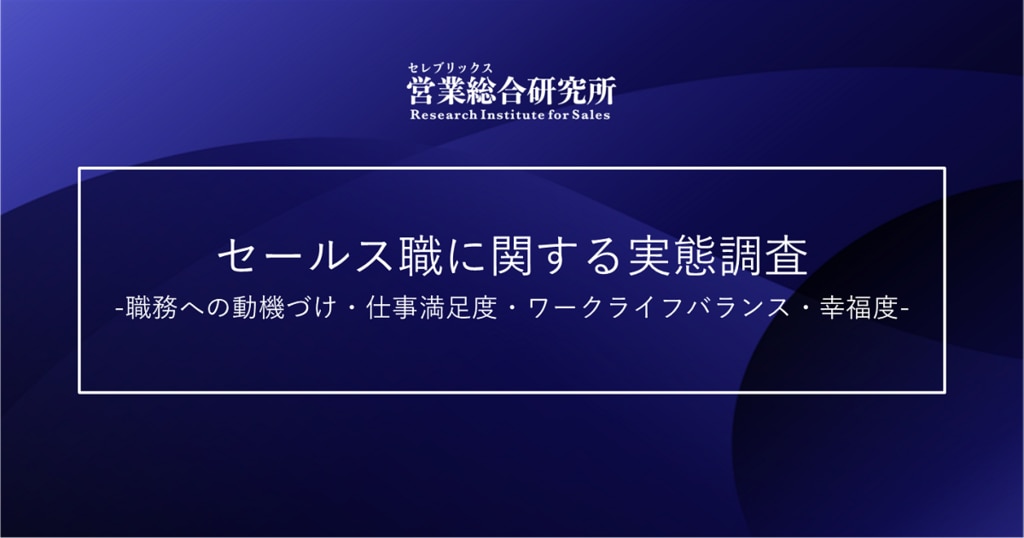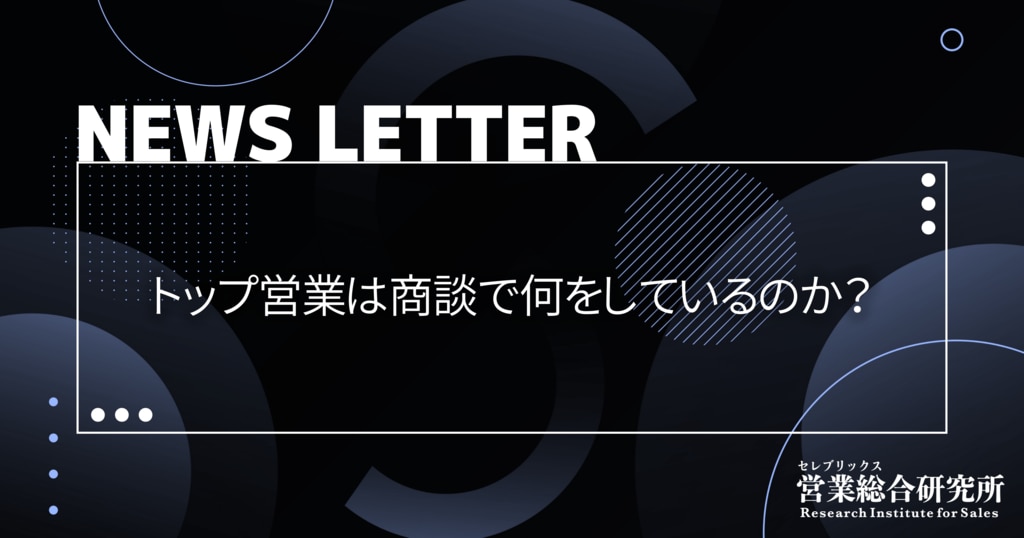『今、なぜセールスパーソンの「非認知能力」に注目すべきか』-デジタル時代の新たな競争力―
目次[非表示]
AI時代に営業職の価値が高まる理由-AIにはできない「人間らしい営業」の本質
近年、AIの進化に注目が集まっています。ChatGPTなどの生成AIや機械学習の発展により、多くの仕事がAIに置き換わる可能性が指摘されています。営業のデジタルトランスフォーメーション(DX)も進展し、営業活動の形は変わりつつあります。しかし、このような時代だからこそ、営業職の重要性はさらに高まると考えられています。
営業職の重要性が高まると考えられる大きな理由は、顧客との関係性の構築が営業業務の中核にあるからです。商品やサービスの説明自体はAIでも可能かもしれません。しかし、顧客との信頼関係づくりや、複雑な状況での臨機応変な判断には、人間にしかできない要素が多く含まれています。
とりわけ、企業間取引(BtoB)の営業では、その傾向が顕著です。商談の過程で生じるさまざまな課題に対して柔軟な発想で解決策を提案するなど、人間ならではの対応力が今後ますます重要になってくるでしょう。
従来の営業研修や教育では、商品知識や営業スキルといった「目に見える能力」の向上に重点が置かれてきました。提案書の作り方、商談の進め方、クロージングテクニックなど、いわゆる「型」の習得が中心です。これは形式知として伝えやすく、また成果も測りやすいという利点があります。
しかし、実際の営業現場で求められるのは、マニュアルには書かれていない「人間ならではの対応力」です。そこで近年注目を集めているのが「非認知能力」であり、この能力の開発と向上が、これからの営業組織における重要な課題となっています。
「非認知能力」とは何か-見落とされがちなセールスパーソンの非認知能力
非認知能力とは、非認知能力はIQテストや学力テストのように定量的に測定することが難しい能力です。具体的には、目標に向かって粘り強く取り組む力(グリット)や、挫折から立ち直る力(レジリエンス)、自己管理能力などが含まれます。
例えば「粘り強さ」や「自己管理能力」は、数値化して比較することが容易ではありません。また、それらは日々の行動や態度、周囲との関係性の中で徐々に表れるため、一時点での測定や評価も困難です。
さらに、本人が意識していない場合も多く、「潜在的な力」という性質を持っています。このように客観的な把握が難しく、時間をかけて現れる特徴があるため、「見えない力」と呼ばれる場合もあります。
営業の現場では、非認知能力が特に重要な役割を果たします。例えば、初対面の顧客との関係構築では社会性が問われますし、商談が行き詰まった時には忍耐力が試されます。長期的な目標達成には、持続的なモチベーションが欠かせません。
こうしたマニュアル化しにくい状況での判断や行動において、顧客の表情や声のトーンから真意を読み取ったり、予期せぬ質問や要望に臨機応変に対応したりと、まさに非認知能力の高さが真価を発揮するのです。
最近の研究では、こうした非認知能力がビジネスにおける成功や長期的なキャリア形成に大きく影響することがわかってきました。特に営業職では、この非認知能力の高さが業績に直結するという報告も増えています。
セールスパーソンに求められる3つの非認知能力
本コラムでは、セールスパーソンにとって特に重要とされる非認知能力の代表例として、以下の3つを紹介します。
内発的動機付け
1つ目は「内発的動機付け」です。これは、外部からの報酬ではなく、仕事そのものにやりがいや楽しさを感じる力を指します。例えば、新しい商品の知識を深めること自体が楽しく、お客様の課題解決に取り組むことにワクワクするといった感覚です。この動機付けは持続的かつ質の高い行動を生み出します。
営業の仕事は日々の地道な活動の積み重ねが求められます。もし外部からの評価や報酬だけをモチベーションにすると、その地道な活動を長続きさせるのは容易ではありません。一方、内発的動機付けがあるセールスパーソンは、顧客との関係構築や提案活動そのものに喜びを見出します。目先の売上目標だけでなく、顧客の本質的な課題解決に優先的に取り組むため、結果として長期的な成果につながるのです。
レジリエンス
2つ目の「レジリエンス」とは、困難な状況から回復し、適応する力のことです。「失敗から学び立ち直る力」「ストレスに対する耐性」「変化への柔軟な対応力」といった要素を含み、誰もが持っている力ですが、経験を通じてさらに強化できます。
営業の現場では、顧客に断られることは日常茶飯事です。商談不成立や顧客からの厳しい指摘、市場環境の急激な変化なども起こり得ます。そうした逆境にあっても前向きさを保ち、失敗から学んで立ち直るレジリエンスこそ、営業活動にとって必須の能力です。失敗を次の成功への学びに変える力や、プレッシャー下での冷静な判断力、予期せぬ事態にも柔軟に対応する力を備えたセールスパーソンは、持続的な成果を生み出すことができます。
グリット(やり抜く力)
3つ目の「グリット」とは、長期的な目標に向かって情熱を持ち続け、粘り強く取り組む力を指します。単なる忍耐力とは異なり、「明確な目標への一貫した関心」と「困難を乗り越える粘り強さ」という二つの要素によって成り立っています。
一般的に、営業の成果は短期間で現れにくいものです。新規顧客の開拓から信頼関係の構築、そして成約に至るまでには、多くの時間と努力を要します。その過程で、新しい案件に気を取られてしまったり、断られ続けることでモチベーションが下がったりするリスクもあります。グリットの高いセールスパーソンは、こうした状況でも本質的な目標を見失わず、粘り強く活動を続けることが可能です。その結果として、顧客との間に長期的な信頼関係を築くことができ、持続的な成果を生み出せるようになります。
これからの営業組織における人材育成のヒント-非認知能力を伸ばすための組織的アプローチ
これからの営業組織は、テクノロジーの利活用と人間ならではの営業力の融合を図る必要があります。特に、非認知能力の開発と向上は重要な経営課題となるでしょう。営業人材の非認知能力を伸ばすためには、組織として体系的に取り組むことが重要です。具体的には以下のポイントが考えられます。
採用段階
従来の営業経験や商品知識だけでなく、「グリット」や「レジリエンス」を見極めるための面接プロセスを検討します。過去の逆境体験とその克服方法、長期的な目標達成への取り組みなどを深掘りすることで、候補者の非認知能力を把握しやすくなります。
教育段階
OJTと集合研修を組み合わせ、数値目標の達成だけでなく、失敗から学ぶ姿勢や粘り強さを育む機会を意図的に設けます。さらに、経験豊富な先輩社員がメンターやコーチとなり、若手の相談相手となって具体的な対応方法をアドバイスする仕組みづくりを行うと、非認知能力の向上につながります。
評価制度
短期的な業績評価だけでなく、非認知能力の成長を評価する項目を加えることが大切です。例えば、新規顧客開拓への地道な努力や、困難な商談へのチャレンジ姿勢、既存顧客との関係深化を図る取り組み、チーム貢献などを評価対象とします。四半期ごとの上司との面談では、これらに対する具体的なフィードバックを行い、成長の方向性を示すとよいでしょう。
おわりに-非認知能力を活かした営業の未来-
AI時代の到来によって、営業活動の形は今後も大きく変化していくと考えられます。データ分析やデジタルツールの活用がますます重要になる一方で、セールスパーソンの持つ「非認知能力」の価値もさらに高まるでしょう。なぜなら、ビジネスの本質は「人と人とのつながり」にあるからです。どれほど高度なAIツールであっても、顧客との信頼関係を築き、長期的な関係を維持することには限界があります。
セールスパーソン個人にとって、非認知能力の向上は大きな差別化要因となります。AIが模倣しにくい独自の強みとして、自身の非認知能力を意識的に高めることが求められます。具体的には、失敗から学ぶ姿勢を持ち、自己改善を習慣化することが重要です。また、顧客との対話を通じて共感力を高め、信頼関係を築く努力も不可欠です。
営業組織の管理職には、新たな役割が求められます。 これまでの成果主義や数値管理だけでなく、セールスパーソンの非認知能力を育成する環境づくりが不可欠です。たとえば、若手営業担当者の成長を支援する教育プログラムの開発や、それを適切に評価・フィードバックする仕組みを整えることが求められます。
デジタル化やAIの進展が加速する中で、「人間にしかできない営業力」の価値は、むしろ高まっています。 今後の営業活動においては、非認知能力をいかに育み、活かしていくかが競争力の鍵を握るでしょう。それは単なる売上目標の達成だけでなく、顧客との持続的な信頼関係の構築にもつながるはずです。
本コラムは、以下の論文をもとに作成しています。
-北中英明、「セールスパーソンの業績と非認知能力についての研究」(研究ノート)、『経営経理研究(拓殖大学)』、Vol.119、2021/3、pp.89-115
|
著者:北中 英明(Hideaki Kitanaka) 拓殖大学 商学部 教授 |
お問い合わせ先
|
〒135-0063 東京都江東区有明3-7-18 有明セントラルタワー7階 株式会社セレブリックス E-mail:eisouken-support@cerebrix.jp |